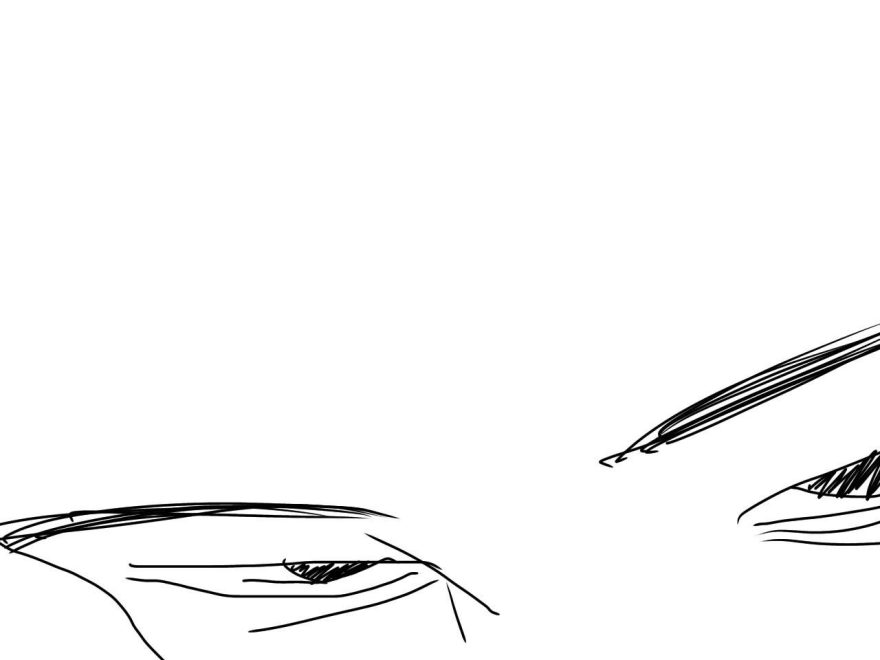著者: こべこべ @kobe_kohbe
紙飛行機は、教室の中で空気を裂きながら飛ぶ。両翼は空調から流れる冷風をはらんで、生徒たちの頭上を滑空していた。まだ授業中だ。数学教師のトイモトが黒板に数式を書いているあいだに、目的地まで飛ばなければならない。大学ノートを一ページ千切って作られた紙飛行機の右翼は、粗い鋸のようなかたちをしていた。
生徒たちの中には、無視をする者や、堪えきれずに失笑する者もいる。波紋のように広がる静かな笑いが、教室中に瀰漫していた。近くにとまった蝉がジジ、と鳴く。トイモトが板書を終えて教壇に戻り、指先を拭きながら生徒たちを一瞥する頃、教室は既にいつも通りの落ち着いた姿に戻っていた。
二学期の中間試験までまだ一ヶ月はあった。高校三年生の夏休み後は、粛然としないやや奇妙な均衡を保った緊張感が、生徒たちの心の隙間を空気のように満たしている。さっきまで飛んでいた紙飛行機は、窓際の列、前から三番目の席に見事着地している。一方送り主は廊下側から数えて三列目、前から二番目の席で、今は真面目を装いながら授業を受けていた。
昼休みまであと二十分。シャープペンシルの頭を叩きながら、彼は現在計画している「あのこと」について考えを巡らせていた。真剣に教師の話を聴く気は初めから無い。おそらく彼は、少なくともこのクラスの中で受験に対する意欲が最も低い生徒のひとりだった。さっき飛ばした紙飛行機と、今考えていることについて、彼は受験生らしい焦燥をまったく感じていない。むしろ自身の行為に深い満足感をおぼえているようだった。
トイモトが再び黒板の方を向く。それを見た彼はすぐ背後を振り返って紙飛行機が飛んでくるのを待った。授業中、彼は相棒とこの遊戯に没頭し続けていたのである。
紙飛行機は教室の天井を撫でるようにして弧を描き宙を滑り、二点を互いに行き交っている。予定されている着地点に変更もなければ、二人のあいだの交通に、何の便りも意味も存在しなかった。折り畳まれた白紙が、微妙な風を受けながらただ夏の暑い午後を時間の矢のように通り過ぎようとしている。それだけだった。
やはり飛行機は飛んできた。きつい角度で射出されると、高度が頂点を迎えたのちに、ほぼ墜落に近い軌道を描きながら紙飛行機はやってくる。彼は両手でそれを迎えようとしていた。鋭い飛行機の先端が迫ってくるようすは、たとえ無音だとしても簡単にあの金属的な轟音を想起させた。手元に落下するタイミングを狙い、形を崩さずに捕まえる瞬間はいつまでも慣れることがない。両手のひらを上に向けて指先を少し曲げる。心の準備はできていた。直前と直後、心はいつも空白になる。紙飛行機は目先をかすめた。
横から太い腕が無作法に伸びてくる。視界がそれを捉えた頃、思いきり握りつぶされた紙飛行機の原型は既にとどめられていなかった。振り向くと、机を真上から覆い隠すようにして、トイモトが彼を見下ろしている。
「サラタ」
彼の名前が呼ばれた。
サラタは春と夏が嫌いだった。それはこの列島特有の温暖湿潤気候や毎年訪れる台風の脅威を恐れているからではなく、日没時間が特に遅延しているからだ。彼は先ほどまで職員室で説教され、下校の時間が大幅に遅れたのにもかかわらず、まだ太陽は地表をかすめるようにして日光を彼のもとへ届け、己がまだ空の支配者だということを誇示しようとしている。そして登下校中、彼はどちらも日光の庇護下にあったわけだから、学校にいた約八時間について、現実の世界とまったく違う、堅い壁で覆われた別の時空間で過ごしたかのように、今日もまた何事も停滞したままだったと思ってしまえるほど、深い退廃感におそわれてしまっていた。だから彼は今、受験とはまったく異なるものに関して、頭を悩ませている。
サラタと共に紙飛行機で遊んでいたのはフクナという名前の、学年内でも特に出来の悪い生徒だった。彼らは同じ道を一緒に歩いている。二人とも大差のない身長だったが、サラタは花壇のブロックの上を歩いていたせいで、今だけ彼がフクナを見下ろすようにして会話していた。フクナは自分の自転車を押している。
「決行は明後日だ」
ポケットに手を入れながら、サラタは言った。フクナは何も言わずに頷く。
「ぼくたちはやりたいようにやる。そうだろ?」
こう話すサラタを、彼はしばしば見つめるだけで何も言おうとしない。サラタは歩いていた花壇が途切れたので、次の花壇に飛び移った。
正直なところ、サラタは彼のことを心底軽蔑していた。皆んなは彼らのことを無二の親友同士だと評していたが、実際のところは、斜に構えすぎて加わるべき集団にも属せなかったサラタが、致し方なく同じように孤立していたフクナを自分のところへ引き入れたに過ぎない。真剣にならないだけで、その気になれば良い成績を取れると自負し、実際まったく勉強せずとも各期の試験では学年の上位に割り込むことのできるサラタにとっては、毎度試験前日になり焦って試験の範囲を詰め込んでも、まったく結果が振るわないフクナは、阿呆そのものとしか思えなかった。
二人は小さな公園までたどり着くと、歩くのをやめた。ここから、帰り道が違う。サラタはフクナともう少し話していたかった。土で汚れたサッカーボールを見つけて拾うと、両手で宙に投げてみる。
「皆んな、どう思うかな」
フクナはようやく口を開いた。
「何とも思わないよ。何か思ったとしてもすぐ忘れる」
サラタはサッカーボールを足元に置いてフクナに向けて軽く蹴ってみた。ボールは自転車の二輪の隙間をうまく通って、彼のところへ届く。
「先生には何て言ってる?」
「江成大を受けるって言ってる」
サラタは質問に応えながら、フクナが一向にボールを蹴り返さないことに苛立ちはじめていた。
「すごいところだね」
「受かる自信あるんでしょ?」
「受ける気ははなから無いさ」
またフクナの方を一瞥する。
「だって計画が成功したら・・・」
続きを言いかけたとき、フクナはそれまで掴んでいたサドルから手を離して傍に自転車を停めた。
彼はようやくボールを蹴り返す。サラタはそれをうまく受け止めるが、もう一度彼の方へ送り返そうとする気にはならなかった。
「フクナは何て言ってる?」
ただ同じ質問を繰り返そうとは思った。
「まだ決まらないって言ってる」
その後は二人ともなぜか伏せ目がちになって、少しのあいだ何も言わなくなった。サラタはひとりでドリブルをしはじめる。
「そっか」
「先生はそれに対して何て?」
そろそろ暗くなりはじめるかもしれない。膝とボールが接触するたびに軽く小突くような音が鳴るものの、周囲にいる人たちすべてを驚かせるほど大きくは響かない。
「早く決めろって」
そう呟かれるのをサラタは聞いた。
フクナと別れたあと、サラタはひとり公園に残った。ただここにしばらく留まっていようと思ったからだった。ドリブルは昔から得意だったから、制服が汚れるまでボールを蹴り続ける。このあいだ、彼は何も考えていなかった。ただ俯きながら、要領よく両脚を交互に動かす。こういうとき彼はひどく深刻そうな顔をして、子供の頃から周囲にさまざまな不安を与えたものだった。しかし実のところは沈鬱さを演じているだけで、彼自身は眠るよりも深く無意識のうちでうずくまっているに過ぎない。それは長年培ってきた彼なりの生存戦略のようなものだった。もう辺りは暗くなった。公園ではまだ小学生たちが遊んでいる。何をしているのかはよく見えない。サラタは蹴るのをやめて、子供たちに大声で呼びかけた。返事がくる。彼は脚に思い切り力を込めて、彼らの方へサッカーボールを蹴り飛ばした。
夕食後、サラタはすぐに自室に戻った。両親は何か言おうとしていたようだが、彼にとって関心のあることではないし、どうせ応えたところで彼らが抱いている心配を少し解消してやるだけの嘘をつくだけだから、そのためにわずかでも頭を使うことが癪にさわるのだ。サラタにとって親とは幽霊のようなもので、目の前にいなければ存在しないも同然だった。たまに視界に現れることがあっても彼自身とはほとんど関わりが無いようで、いつも限りなく遠い距離を感じてしまう。そして彼はひとりになると、本当に両親のことを忘れてしまっているようだった。
ベッドの上にあぐらをかいて座ると、静かにノートPCを開きファイルを開く。文書と添付された地図が表示され、彼は慣れた手つきでそれを確認しはじめた。
『下校後、公園前に集合。(親には互いの家に止まると言っておく)。(用意する物は末尾に記載)。公園から団地を抜けて、アナヤ川沿いの土手を北へ進む。(帰宅する同級生や教師に見つからないよう大通りや最寄り駅周辺は近づかない)。アナヤ橋を渡ったあとワモト駅に乗る。(以降はなるべく人通りの多い場所を歩く)。・・・・・・・・・』
窓には暗がりが貼り付いているようだった。彼は夜明けまで起きていられたことが一度もない。しばらくすれば、すぐ眠くなるだろう。彼が姿勢を変えると、ベッドの下のバネが体重を支える。
部屋には内側から鍵がかかっていた。だから誰も侵入することができない。彼は今日の日付けを見る。もう、九月だ。彼は今まで何度も考えてきたであろうことについてもう一度考え直してみる。残りの時間を受験勉強に費やすか、どこか見知らぬ土地の匂いを嗅ぎながら風塵のように生きるか。一度家を出てしまえばしばらくは帰ることがないだろう。帰るべきときに帰ればいい。そう反芻するが、この思考こそが彼の経験と知恵の狭隘さの露呈にほかならなかった。
フクナに電話する。案外すぐに応じてくれた。準備は出来ているかと聞くと、か細い声で返事をしてきた。不安げな声だった。なぜフクナをこの計画に誘ったのか、彼自身よく分かっていない。しかし誘うとき、きっと彼は断ることが「できない」だろうという確信していた。彼と話しながら地図に示された道筋を目で辿る。途中で通るアナヤ川の土手は、江成大のカヌー部が大会に向けてよく練習をしている場所だった。サラタは江成大を第一志望にしている。彼にとって合格するのはやや難しい大学だったが、周囲はそれなりに期待をかけてくれていた。しかし、この大学を志望している当の彼自身が、入学することは不可能だと悟っていた。それは勉強をしないからではない。努力したところで初めから無理だと知っていたからだ。それに気がついたのは、三年になる直前だった。
「じゃあ、もう寝るよ」
フクナが話しているのを遮って、一方的にサラタは通話を止めた。フクナが何を話していたか、よく聞いてはいなかった。
翌日は全教科が短縮授業で、いつもより早く下校できそうだった。彼は放課後にまたフクナと集まって、ついに明日決行される計画について最終的な打ち合わせを行う。とは言っても既に何度も確認されている事柄を理解できているか、もう一度互いに示し合わせるだけだから、すぐに終わってしまうだろう。
「荷物は最低限に」
フクナは頷いた。
「できる限りいつも通りの服装で」
もう一度頷いた。
「誰にも漏らしてないな」
頷いた。
「予算はどうだ」
そう訊かれるとフクナは学生鞄から茶封筒を取り出した。
「あ、バカ」
サラタはつい声を出してしまう。
「お金はできるだけ目立たない方法で保管しろと言っただろ、その封筒じゃすごく不自然だ」
「ごめん」
フクナは正直そうに謝った。
相変わらず空は晴れていた。二人は今誰もいない教室の隅にいる。放課後ここに残って勉強をしようとする同級生は皆んな追い払っていた。蝉は一時期よりも少なくなったが、窓の近くにいるとけたたましく鳴いているのを嫌でも理解させられる。彼らも長居するつもりはない。ただもう少しここにいようとは考えていた。
「合計で二万と百五十円」
「少ないな」
「これでも集まった方だと思うよ」
「まあ、詐欺で集めたからなあ」
サラタたちは学内の学生たちから計画実行のための資金を「困窮する子供への国際的な支援」と言って集めていた。
「ぼくたちみたいな人間は日本中、世界中に存在してる」
サラタは少し苛立っている。フクナはそれを真面目に黙って聞いていた。
「この金額の少なさはぼくたちを嘲笑しつつ黙殺しようとしてる奴らからのボウトクだ」
「こういう連中が大手を振るって歩ける街の外れにさえぼくらは住んでいたくない」
「明日の決行が待ち遠しいよ」
そんな仰々しい言い回しに、フクナは何かを言って付け加えたり、反論したりとすることを決してしなかった。
誰かが教室に来る。ドアを開ける音がして二人が振り返ると、担任のコバがそこにいた。
「何を企んでるかは分からないが、もう問題は起こさないでくれな」
まだ二十代の若い教師は、完全下校の時間が近づいてもなお帰ろうとしない二人を、軽くたしなめてすぐ帰ってしまった。その背後を、サラタは執拗な眼差しで睨み続けている。だが彼自身、コバに対して特別で具体的な怨恨があるわけではなかった。実際、彼の胸の中にある暗い衝動は、なぜ彼をここまで過激な行動に駆り立てるのか不思議なほど、空虚だった。おそらく、それを彼は自覚していないし、知ったところで何の反省にも繋がらないだろう。
「先生、この前のことも色々と庇ってくれてたそうだよ」
注釈をするようにフクナは言った。しかしサラタはほとんど聞いていない。外はまだ明るいままだ。
当日。サラタは公園前でフクナを待っていた。すべてが予定通りに進行している。特別目立つような服装はしていない。荷物も片手で運べる程度の重量だ。今日は一日中曇天で、街全体が薄い灰色に覆われたような感覚をおぼえる。公園では何人かの子供がいたが、誰も彼のことを見てはいなかった。強い風が百日紅や椿の木を一斉に揺らしている。
遠くからフクナが来るのが見えた。サラタは座っていた花壇のブロックから腰を上げて、彼を迎えようとする。だが、何かがおかしい。目を凝らすと、彼は徒歩とは思えない速度で接近している。自転車だ。サラタは激昂が喉の奥から一瞬で迫り上がってくるのを感じた。これから人目を忍んで蒸発する奴が、なぜ自転車を必要とするのだろうか。瞬く間に彼は追いついてきた。
「ごめん」
彼は言った。遅刻はしていない。予定通りだった。サラタは無言になり、白い顔で彼を見つめている。もう一度帰宅させて仕切り直そうか、それともこの場に自転車を乗り捨てようか。単純な選択肢と、止めどない怒りが頭の中をぐるぐると回っていた。
一方フクナは遣る瀬無い表情をしながらポケットの中をまさぐっている。二人のあいだに少しの時間沈黙が生まれたが、それもすぐに打ち破られた。
「ごめん」
フクナは素早く、そして力強くサラタの手を取ると、手の平にあの茶封筒を握らせた。サラタは一瞬混乱する。何を問いただそうかと舌をもつれさせているうちに、フクナはまた自転車のペダルに脚をかけた。
彼は行ってしまった。ひとり残されたサラタは二万円の入った封筒を握りしめて、しばらく立ちすくんでいた。裏切られたことをようやく理解するまでに時間は要しなかったが、理解したあとも激しい虚脱感が冷水のように彼の心を浸して、この季節がまだ熱気をはらんでいることを、束の間だけ忘却させた。
だが、彼無しでも計画は遂行できる。サラタは改めて体勢を整え直すほどでもないと判断した。事態が思わぬ方向に向かっても構わずに猛進するだけの行動力は、まだある。むしろ、それしかないと言えるほどだった。
サラタは何度も見て覚えた地図を思い出しながら、長い距離を歩きはじめる。できるだけ人気の少ない道を選ぶから、自然と道のりは複雑になった。土手に着く頃には、もうだいぶ遅くなっているだろう。同じ地区に住んでいながらまるで別世界のように思える古い住宅街や長屋の痕跡を辿りながら、慎重に自然に進んでいく。歩きながら彼はさまざまなことを考えた。見事に姿をくらませたあとは何をするべきだろうか。しかし彼は「べき」という言い回しが嫌いだった。彼はあくまで、自分の望んだ方向にだけ生きていきたい思っている。
これからはひとりだ。フクナには裏切られた。途中からはこればかりが脳裏をよぎって、言葉にできないような感情が鳩尾と喉元のあたりを掻きむしる。大きいガラスの玉を飲み込んだかのような息苦しさを、彼は感じた。気づけば、狭い路地に迷い込みひとりで泣いている。ここがどこだか、よく分からない。泣いていることを彼は認めたくなかった。少なくとも周囲に誰もいないだけ幸いだ。曇り空がやや橙色に染まっている。こんな天気でも夕焼けを見れるのだと、泣きながら彼は思った。
近くで、聞き慣れた声がした。よく耳を澄ますと、それはトイモトの声だ。
「計画がばれた」
咄嗟にそう思うと、彼は声のする方へ近づいて、路地の抜け道を見つけた。顔を少し出して、トイモトの背中が十数メートル先にあるのを確認する。フクナがあとあとすぐに計画を漏らしていたとしたら、彼らはあの地図のルートを知っているはずだった。そしてここにトイモトがいるということは、サラタはまだ本来のルートからほとんど外れてはいないということになる。トイモトが去るのを待って、また道を探しはじめた。
ルートが知られている以上、もう同じ道は通れないだろう。サラタは敢えて、大通りを利用することにした。狭い道なら見つかれば八方塞がりになりやすい。しかし人通りの多いところならば、すんでのところで逃亡できる余地はあり、人混みをうまく利用できると考えたからだ。今は下校中の学生や退勤するサラリーマンが密集する時刻のはずだった。
大通りに出ると、案の定人が多い。その中に紛れるようにして、今度は堂々と橋を目指しはじめた。いつのまにか涙は止まっている。あいつがいなくても計画は成功する。彼は確信した。
行く先で巡査が二人集まって何かを話し合っている。彼は嫌な予感がした。しかしこの道を通らなければ目的地まで辿り着けない。駅を使うことも既に知られているだろうから、予定よりもだいぶ遠くまで歩かなければならなかった。今ここで彼が踵を返せば、余計に怪しまれるだろう。巡査たちの目の前を通り過ぎてたとき、何かが彼の肩を触れた。
「しまった」
咄嗟に正体がばれたのだと思い、サラタは走り出す。後ろを振り返ってはいけないと感じた。
背中越しに巡査が彼を呼んでいた。だが彼は決して返事をしない。通行人と何度も体をぶつけた。転ばないようにすぐ体勢を整えながら、川の方まで走っていく。まだ巡査の声が聞こえた。
無我夢中で走っているあいだに、川を挟む土手までやって来た。体力を消耗しきって、彼はもう息をするのがやっとだった。彼らからの追跡を振り切るには、もっと遠くまで離れねばならない。サラタは約百メートル先にあるアナヤ橋を見つめた。目を凝らすことにも体力がいるのだと、初めて知る。またすぐ走り出そうとするが、彼にはもう疾走するほどの力は残っていなかった。全身を引きずるようにして、歩きはじめる。
巡査が自転車を漕いで接近してきた。もう彼が捕まるのは時間の問題だろう。だがそれに気づくことさえ、今の彼には難しかった。ただひたすら歩いていく。土手から見える景色は綺麗だった。太陽はもう落ちかけて、周囲の低い住宅の頭を均すようにどこまでも夕空が広がっている。ジョギングをしている夫婦二人に、サラタは追い越された。橋の上を車が通過しているのが見える。
脚を踏み外してサラタは土手の下に転がり落ちた。疲弊して霞んだ目に、五人ほど体格の良い男たちが見えた。
「その子を助けてあげてくれ。ようすがおかしいんだ」
巡査が土手の上から男たちに向かって呼びかけた。
サラタは虚な頭の中で、この男たちが江正大の学生であることを少しずつ思い出しはじめていた。彼らから肩を貸してもらうと、湿っぽい川の臭いがする。嫌な臭いだった。視界の隅に、一艇のカヌーが見える。サラタの華奢な体をカヌー部の男は軽々と抱えて、ひと言声をかけた。
「大丈夫ですか?」
そのとき、彼は心の中よりも体の外側から何かに突き動かされるようにして、男の体を振り切った。直感的に閃いたようで、まともな考えなんてない。土手の間際までまた駆け出して、一本のパドルを拾った。サラタはこのときようやく少しだけ頭が冴えてきたが、このあと自分が何をしようとしているのか、いちいち説明づける必要もないと悟り、追ってきた巡査やカヌー部の部員を近づけまいとパドルで威嚇する。
ひとり、彼に向かって飛びかかってきた。パドルを振り上げて、思い切り頭を殴る。うまく当たり、部員はその場で頭を抱えて唸りじめた。それを見た巡査が駆け寄ってくる。うまく間合いを詰めてサラタは巡査の腹を突いた。倒れた部員に覆い重なるようにして、巡査は嗚咽したまま気を失った。息を弾ませて周りを見ると、もう彼を捕まえようとしている者は誰もいなかった。残された部員たちも、ただ混乱しているだけで何もしてこない。
土手の上から見慣れた顔が見えた。サラタの両親だった。それに続いて、見覚えのある教師や同級生が現れる。サラタは捕まることだけは避けたかった。ゆっくりと背後に下がり、カヌーを川岸に押し出す。よく見れば二人乗り用だった。カヌーに乗ると、パドルで岸辺を突いて、慎重に船を漕ぎはじめた。皆んなが追いついても、もう遅かった。既に手を伸ばしても届かないほど、彼は離れてしまっている。
結局は素人の操縦だった。パドルは使いこなせず、カヌーは今にも転覆しそうになっている。よろめきながら彼は水上に浮かんでいるしかなかった。汗と泥で汚れた体を、夏の強い風がどこかへと連れ去ろうとする。次第にカヌーは川の中央へと運ばれて、彼は簡単には脱出できなくなってしまっていた。彼はパドルを捨てる。荷物だけは汚すまいと、両手で強く抱えていた。ときおり、羽虫の群れに遭遇する。
土手を見ると、両親やほかの皆んなが、彼を追いかけて、彼と並行に走っていた。静かな水の上だから気づかなかったが、このカヌーは彼が思っている以上に速く進んでいるらしい。しばらくすると、ひとりずつ走るのをやめはじめた。そして遠い目をして、離れていく彼のことを見つめるようになる。橋の下をくぐる頃には、もう二、三人しか彼を追う者はいなかった。
最後まで彼を追いかけていたのは両親と担任のコバだけだった。しかし夜が訪れるにつれ、それぞれが誰の顔なのかも判別がつかなくなる。街の灯りで影の輪郭は見えるのだが、最後のひとりが走るのをやめたのを見ても、それが誰なのかも分からなかった。
サラタはもうすべてに疲れきっていた。固い結び目を解こうとすると人は一種の無感動に達するが、彼も同じような心境に立っている。虫の鳴き声だけが彼の世界を支配していた。これほど暗い夜を、彼は体験したことがない。左右にある土手の向こうには漁火のような灯りがあるが、それも宇宙の星雲のように、遠くから彼を見下ろしているに過ぎない。彼は今、ただここから川へ落下しないことだけを考えていた。落下しなければ、いつかこのカヌーは海に出るだろう。だがそれまでどれくらいの時間がかかるか、彼には見当もつかなかった。海に出たところで、できることはない。サラタは、もう泣くこともできなかった。
サラタを呼ぶ声が聞こえる。もう暗い影で染められた輪郭しか見えなかったが、明らかに人の声だった。カヌーから落ちないように身をねじって彼が目を見張ると、その影は追いかけてくる。土手の上から彼に手を振っていた。サラタは声ですが分かった。あれはフクナだ。フクナはほかに誰もいない土手から、必死に彼を呼んでいた。カヌーは真っ直ぐ流されていく。サラタと一緒に、同じ速度でフクナは走り続けていた。