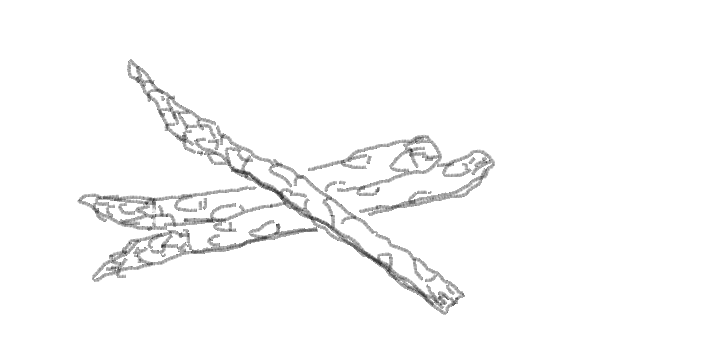人々の列に交じって、先頭車両の通路を前から後ろまで、歩いた。所々荷物を棚に上げようとする人が通路をふさぎ、そのたびに立ち止まった。そのようにして手元にある切符と、荷物棚の下に書かれた座席番号を1Aから25Eまで見比べていった。大晦日だというのにそこそこ混んでいた。家族連れもかなり居た。
席が見つからないまま2号車との連結部分まで来てしまった。振り返ると人の列はますます長くなっていて、通路は満杯になっていた。切符を確認した。自分の席が1号車にあることは間違いない。席にたどり着けなかったので引き返さなければならないのだが、これでは先頭車両に戻ることすらままならない。行列から外れて、出口ドア前のスペースに一旦よけた。
そこには中学生のころの同級生がいた。結構仲が良かったはずなのに、卒業してから一度も会っていなかった。
車両の音響設備から、流行のサイケデリックロックバンドの楽曲が流れてきた。先頭車両の方を向いたまま、そいつと並んで、大声で歌った。アスパラガスがどうこうとか、そんな歌詞だ。通路を進む行列は構わずこちらの方向へ歩いてきた。皆胡散臭そうにこちらをジロジロと見たが、誰も立ち止まらず2号車の方向に消えていった。そもそも誰ひとりとして自分の席を探そうとしていなかった。
楽曲の最後のサビになっても、列は全く途切れなかった。最後のサビで女性ボーカルのコーラスが入るところが、この楽曲の一番美しいメロディーだ。その部分をひときわ大きな声で歌った。二人の歌声とコーラスが絡み合うのがきもちいい。
そのとき列の中に、頭一つ抜けた、黒づくめの恰好をした若い男を発見した。そのへんにいくらでも居そうな奴だったが、なんだか不気味だった。思わず少し歌声を控えた。色白で、黒髪のマッシュヘアーで、シルクみたいな生地の大きめの黒シャツを着ていた。鰻のように細長く、ツルツルと掴みどころがない、そんな印象の人間だった。そいつはかなり長い間こちらを睨んだ。
しばらくして列が途切れ始め、ついには通路を歩いている乗客がいなくなった。少しすると先頭車両のドアも閉まった。音楽が止んだので、ふたたび自分の席を探すために、先頭車両に戻った。
内部は様変わりしていた。空間全体を覆う光が、味気ない蛍光灯のものから、赤と緑のカクテルライトのものに変わっていた。そして先ほどまでは座席が並んでいただけだった空間には、いくつもの円卓が出現していた。ライトは空間全体を照らすには少し暗すぎたので、円卓を囲む人々は背景に溶け込んで見えづらくなった。それぞれの円卓には白いテーブルクロスが敷かれていて、そこだけがまるで睡蓮の葉のように目立っていた。
ある一つの円卓に、先ほどまで車内音響から流れていたサイケデリックバンドのメンバーが集まっていた。仲間内で話すこともなく、ただ無言で座っていた。彼らは若い世代のファッションアイコンでもあった。服装に奇抜な色を取り入れながら、総合的にはうまくまとめていた。全員集まるとなかなかに壮観だった。
再び切符を確認しようと目を落としたとき、不意に自分の服装を自覚した。白地に青のボーダーが入ったTシャツで、生地は家庭科で作るエプロンのようにごわごわしており、ボーダーの幅は1本ずつ異なっていた。あるラインは小指ほどの幅で、あるラインは竹定規ほどの幅があった。好きなバンドのメンバーに会えた日に、よりによってこんな奇妙な服装をしていることを恥じた。
バンドが座っている円卓の近くまで来た。恥ずかしい服装ではあるものの、彼らと話すまたとない機会であることは間違いない。一番手前に座っているメンバーとの会話を試みた。彼が担当している楽器は何だっただろう?近寄っても目は合わなかったが、構わず話しかけた。
「あれ、もしかして、」そうしてそのバンド名を、あくまで控えめに、昂っていた感情をできるだけ抑えるようにして言った。「……の方ですか。僕、変なところに迷い込んでしまったみたいですね、自分の服装がこんなにも浮いているので、場違いだなって気づきました、あはは」
自分のことばかり話した。そのメンバーはそこで初めて気が付いたらしく、こちらを見た。色黒で、茶色い長髪にきつめにパーマをかけた男だった。立ち上がればかなりの大男だろう。
「そうなんですか。分かってる顔で喋るから、あなたには全部分かってるのかと思いました」その男は冷たく言った。
それから円卓の周りにいるメンバーに順番に話しかけに行った。小柄なキツネ顔の男や、ちょんまげツーブロック男などがいた。全員に同じようなことを言われて、あしらわれた。一人は茹でたアスパラガスを食べていた。
やはり自分などが話しかけて良い相手ではなかったのだと、速足でその円卓を離れ、席をまた探し始めようとしたとき、彼らに話しかける者が他にも存在することに気付いた。先ほど先頭車両の列の中にいた黒づくめの男だった。いや、よく見ると、その男はメンバーに話しかけている、のではなく、彼らから話しかけられて、いた。会話の内容が聞き取れないどころか、その表情も読みとりづらかったが、バンドメンバー達は熱心にその男に話しかけ、男は微笑み、「あはは、ああ、そうですか」といった感じで相槌を打っていた。男は明らかにメンバー全員から気に入られていた。しかしあの男もまた、バンドの一介のファンに過ぎないことは間違いない。バンドを応援する熱意だってこちらのほうが持ち合せているはず。この先頭車両は洗練された人間で回っているという、ただそれだけのことだ。
【その日のワイドショー】
男性アナウンサー「アスパラガスの卸売業者には、意外な工夫があったんです」
一般家庭に並ぶアスパラ料理の映像。ナレーションが入る。食卓に欠かせないアスパラガス。しかしあなたは、アスパラガスの卸売業者の間で、こんな工夫があったことをご存じでしょうか。
リポーター、アスパラガスの卸売市場。開けた空間、いくつものアスパラガスが整列されてコンテナに収められ、床に並んでいる。
リポーター「こちらは都内にあるアスパラガスの卸売市場です。見ての通りたくさんのアスパラガスがここから出荷され、都民の食を支えているのですが、実は」白い手袋をはめたリポーター、ひとつのコンテナからアスパラガスを一本取り出す。カメラがズームアップ。茎の表面に文字が彫られている、”宜しくお願い致します”と。「文字が彫られているんです」
CGとナレーションによる説明。それによれば、アスパラガスの卸売業者は、農家が商品を納入する際、ひとつひとつにナイフでコメントを彫らせる。卸売業者はそれらをひとつずつチェックし、字が綺麗なものや、漢字の書き順が正しく彫られているものだけを選んで出荷する。基準に満たないアスパラガスの買取は行わず、農家に返品。いつまでたっても改善されない農家とは取引をやめるという。
卸売業者の中間管理職に対するインタビュー。
中間管理職「うちはね、そういう農家の方しか相手にしない。このようにしてみなさまの、食の安全を守っています」
スタジオに戻って、コメンテーター、男性アナウンサーから意見を求められる。
コメンテーター「これはね、書き順で選別しているってところ?(語気を強める)ここがポイントなんですよ。書き順なんて小学生の時くらいしか指導されないでしょう。そこで真面目に授業を受けてきたような、そういう人間の作ったアスパラガスしか基準をクリアできない。家柄というかね、親御さんの教育環境もわかりますし、なにより人間は変わりませんから。小学生のころ不真面目だったような人間が、真面目に仕事なんてできるわけがないんだもんねえ」
なるほど、良い取り組みだな、と思う。ふと気づいて時計を見たら、年が明けてもうかなり経ってしまっていた。車窓からは初日の出が見えそうだ。その通りだ、ずーっとこうやってダラダラしている。どうしようもないな、俺は本当に。