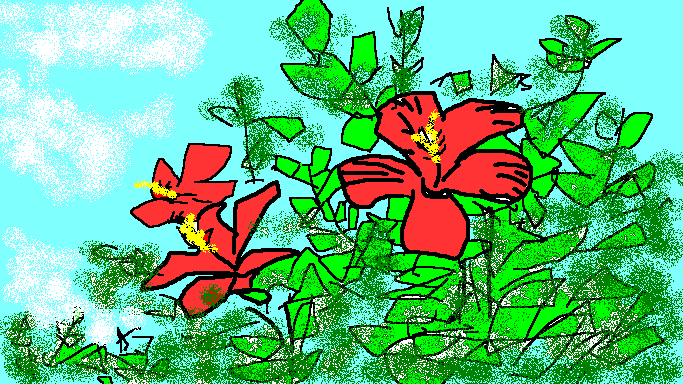その人は本当に元気な人だった。夏になるとよく原色のTシャツを着た。黄色や水色の布地が真っ白な肌によく映えた。僕の知らないバンドのTシャツを夏になるたびにたくさん買うのだ。その人はロックバンドが好きで、毎日毎日新しいバンドを見つけては僕に教えてくれた。僕は音楽に疎かったので、その人が着ていたTシャツの文字を必死に覚えて、TSUTAYAでそのバンドのベスト盤を借りた。喜んでくれると思って、ウィーザーのファーストアルバムのTシャツを古着屋で買ってみた。
「ダサいね」と、その人は言って、笑った。
その人はあの頃の僕とどんな気持ちで一緒にいてくれていたのだろう。僕は大学を卒業して、特に夢も、やりたいこともないまま、自堕落な生活を送っていた。その人は僕が何を言ってもよく笑ってくれた。「面白いよね」「芸人みたいだよね」とよく言った。友達もおらず、その人の他に喋る相手もいなかった当時の僕にとって、どれだけありがたい存在だったことか。
とはいえ、最初の頃は、よく喧嘩もした。その人は旅行に行きたがった。夜は歓楽街で飲み歩くのが好きだった。しかし当時の僕には当然ながら金がなかった。その人が旅行の話を持ち出すたびに、僕は適当な理由をつけて断った。その頃の僕には、金がないと正直に言うことすらできなかった。そういう妙なプライドだけは一丁前に持ち合わせていた。しかしそんなことは全てお見通しのその人は、僕のその不正直さを嫌がった。
その人は一流といわれる大企業に勤めていた。僕がその人の金で旅行に行くことさえ承諾すれば、年に何度でも旅行に行けた。僕より数年年上で、順調に出世もしているようだった。会社でも、他のところでも、出会いだっていくらでもあっただろう。それでも、一人で僕が暮らしている阿佐ヶ谷のボロいアパートをよく訪れ、僕の分も一緒に食材を買ってきてくれ、二人で料理をした。本当は、外食だってしたかったはずだ。それでも、外で料理を奢られることはやはり僕の小さなプライドが許さなかったのだ。
僕は時々不機嫌になった。それは生活に困窮しているからでもあったし、昼夜が逆転して体調があまりすぐれない時期が多かったからでもあるし、もしくは生来的な性格のなせる業でもあった。それでもその人は定期的に家へ来た。僕の様子がすぐれないと見ると、無理に話しかけてくることはせずに、黙ってずっと家にあったギターを弾いていた。僕が昔何かの間違いで買って埃をかぶっていたギターを、その人はよく僕と話ができない時の暇つぶしに使った。僕はその間ずっと無言でテレビを見ていた。編集で足された笑い声と下手くそなアルペジオがぶつかり合って夜に消えていった。
何年かが経ち、僕は友達に誘われて小さなベンチャー企業に入社した。その友達が仲間と数人で起業した会社だった。大昔の貨幣をコレクター向けに売るとか、そういう会社だ。僕が入社した直後に、事業は急激に成長した。僕は急に忙しくなった。しかし、それまでの自堕落な日々の苦しみと比べれば、仕事の忙しさなど何も辛くなかった。僕は毎日夜中まで社長である友達と都内を駆け回り、顧客に応対し、取引先と話し合った。それでも業務量が消化しきれなくなってくると、僕たちは従業員を雇った。一人、また一人と。いつの間にか会社は大きくなっていった。僕は初期メンバーだったので、自然と重役に就くことになった。ちょっと驚くような額の収入が毎月入ってきた。
僕はよく家を空けるようになった。毎晩遅くまで業界人たちと飲み歩いた。重役になった僕達はもはや通常の業務をせず、同じ世界の重要な人間たちと飲み歩くことが仕事となった。
あの人は、それでも変わらないペースで僕の家に来た。渡しておいた合鍵で入り、一人でずっとギターを弾いていた。時々聴かせてもらうと、その余りの上達に僕は驚いた。その人がギターを弾いているところさえも見ることがなくなったから、久しぶりに会う親戚の子供の成長のように、その上達は急激なものに感じられたのだ。そして毎日午前二時や三時にタクシーで帰宅する僕を迎えてくれた。軽い食事を作ってくれていて、ほとんど毎日一緒に食べた。その人は時には朝まで寝ずにいて、そのまま仕事に行った。
会社が大きくなり余裕が出てくると、僕は時々休みをもらえるようになった。ずっと連れて行けなかった旅行に、その人を連れて行く余裕ができたのだ。
しかし、今度はその人の方が何かと理由をつけて旅行を断るようになっていた。時々行くことはあるにしても、それは都内近郊で、しかもすることといえば、海辺を歩いたり、美術館に行ったりとゆったりとしたものだった。その人は早々にホテルに戻りたがり、僕たちはどんな歓楽街にいても飲み歩くこともなく、早い時間に自室に戻った。そうして、二人でベッドの上に横になり、普段忙しくてろくにできていない会話の埋め合わせをするように、長い時間話した。こうしているのが一番幸せ、とその人は言った。
その人は、夏になってもカラフルなTシャツを着なくなった。いや、正確にいえば、もう新しいバンドTシャツを買うことをやめてしまった。バンドTシャツを着るときは何年も前に着ていた色褪せてヨレヨレになってしまったものばかりになったのだ。新品は、無印良品で買ってきた白とか、ベージュとか、紺の無地の服をよく着るようになった。というか、そもそも、新しいバンドを見つけてこなくなった。一番好きだった、90年代周辺のロックバンドのアルバムを、何度も繰り返し聞くようになった。
僕たちは結婚した。でも、結婚した直後にその人は体調を崩してしまい、しばらく東北の実家に帰ることになった。僕は仕事の都合で東京を離れるわけにはいかなかったので、その人についていかず、都内で一人暮らしを始めた。その人からはよく手紙が来た。何度も心配するなと言ってきた。僕は必ず返信した。
深夜、一人で僕はかつての僕の我儘さについて考えた。そして、僕が吸い取ってしまったようにも感じられる、その人の元気について考えた。あの頃鮮やかだったバンドTシャツたちが色褪せて行くように、その人もどんどん色褪せてしまったように感じられた。そして、対照的に、今や生きがいというべきものを見つけ、毎日楽しい日々を送っている自分のことを考えた。
その人は、手紙にハネムーンに行きたいと書いて寄越した。僕は心配した。体調が完全によくなるまで、遠出は後にしたほうがいいんじゃないかと提案した。しかし、その人は意地でも今、ハネムーンに行くのだと言って憚らなかった。僕は嫌な予感がした。まさか、ドラマみたいに余命何ヶ月の花嫁になっているわけはないと思ったが、それにしても、その人は当分先が見えないトンネルに差し掛かっているのではないかと気が気で仕方なかった。
ハネムーンの舞台は沖縄に決まった。その人の体調のことを考慮し、海外は避けた方がいいだろう、ということで身内の意見はまとまった。その人と出会ってから十回目の夏が訪れようとしていた。
僕たちは沖縄の高級リゾートホテルに宿泊した。きれいな海が一望できる部屋だった。僕はその人の体調のことを考え、部屋からあまり出られないことも考慮したうえでその部屋をとった。しかし、チェックインした直後から、その人は外へ出たがった。僕は少々驚きながらも、ホテルの目の前の砂浜へと向かった。
陽が傾きかけ、オレンジ色のラインが一筋砂浜と並行に海の上に浮かんでいた。ミキサーで混ぜたみたいな雲がやや火照りながらたくさん浮かんでいた。湿り気を帯びた砂浜には我々以外誰もいなかった。砂浜は見えなくなるところまでずっと続いていた。
「よかった、来れて」その人は、僕の方を見て本当に嬉しそうに言った。
僕は無言でその人の顔を見た。何か良くないニュースが飛び込んでくるのではないかと気が気ではなかった。その人の顔は夕日の下でも驚くほど白く見えた。その人は少し眩しそうに顔を顰めながら海の方に向き直った。その表情からは何も窺い知れなかった。